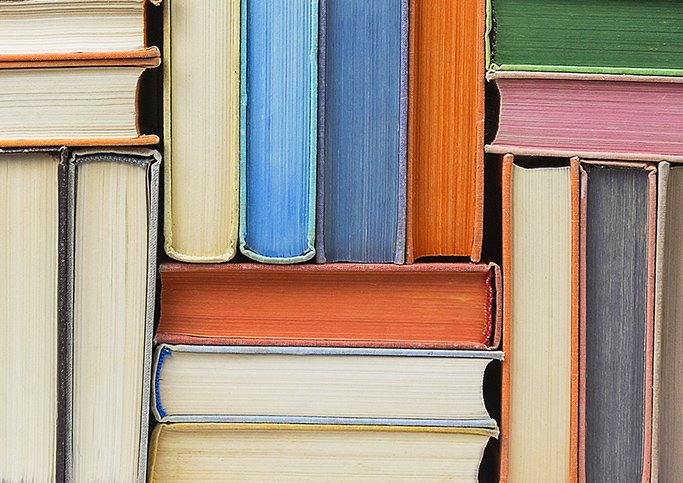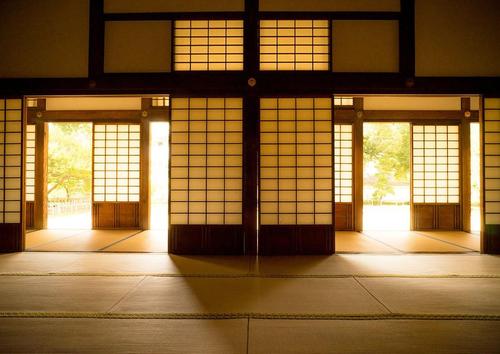日本のお笑い文化のひとつに「漫才(manzai)」があります。「漫才(manzai)」とは、二人一組の芸人が滑稽な会話をして観客を笑わせる芸のことです。今回は、「漫才(manzai)」の様式や「漫才(manzai)」の歴史などについてご紹介しています。
1. 「漫才(manzai)」の様式
「漫才(manzai)」とは、二人組が滑稽な会話をして観客を笑わせる、伝統的な芸のことです。
これは、故意に滑稽な言動をする「ボケ(boke)」とそれを指摘する「ツッコミ(tsukkomi)」の二つの役割を分担して行います。「漫才(manzai)」をする芸人は、スーツを着て「漫才(manzai)」を披露するのが一般的です。これは、観客が話の内容に集中できるようにするためと言われています。
「漫才(manzai)」の題材は、日常生活に関連するものが多いです。「漫才(manzai)」は予め決めた内容を披露することが多いです。ときには、芸人が観客に対して質問することや、観客の反応によってその場で考えた台詞などを追加することがあります。このように「漫才(manzai)」の特徴は、自分たちのやりたいことをやるだけでなく、観客の反応も作品の一部になっていることです。
日本の西側の「漫才(manzai)」は「上方漫才(kamigata manzai)」と呼ばれ、その他の地域の「漫才(manzai)」とは区別されます。「上方漫才(kamigata manzai)」の特徴は、速く勢いよく話すことです。
2. 「漫才(manzai)」の基本用語
「漫才(manzai)」で使う基本的な言葉をいくつかご紹介します。
- ボケ(boke)
「ボケ(boke)」は、あからさまな間違いを言ったり、冗談を言ったりするなどの滑稽な言動で観客を笑わせることです。これがなければ笑うところがないので、「ボケ(boke)」は「漫才(manzai)」を成立させるために必要なものです。
- ツッコミ(tsukkomi)
「ツッコミ(tsukkomi)」は、「ボケ(boke)」のおかしなところや間違いを指摘することです。「ツッコミ(tsukkomi)」は、笑いどころを明確にし、観客に面白さを伝えやすくするという役割があります。「ツッコミ(tsukkomi)」をする時に、「ボケ(boke)」を言った相方の肩や頭を軽く叩く人もいます。
- ノリ(nori)
「ノリ(nori)」は、雰囲気やその場の流れに調子を合わせることです。「ツッコミ(tsukkomi)」の一種に「ノリツッコミ(noritsukkomi)」というものがあります。「ノリツッコミ(noritsukkomi)」とは、相方の「ボケ(boke)」に対して一時的に同調してから「ツッコミ(tsukkom)」をすることです。つまり、「ノリツッコミ(noritsukkomi)」は自分一人で「ボケ(boke)」と「ツッコミ(tsukkom)」の両方を行います。
- フリ(furi)
「フリ(furi)」とは、「ボケ(boke)」へ導くための伏線のことです。これは「ボケ(boke)」の前に「フリ(furi)」を行うことで、「ボケ(boke)」をわかりやすくする効果があります。さらに、「フリ(furi)」は「ボケ(boke)」の意外性を強調することもできるので、観客は予想外の展開にさらに笑います。
[日本のことが気になる?一緒に日本語を学びませんか?]
3. 漫才(manzai)でよく聞くフレーズ
「漫才(manzai)」でよく使われる言葉をご紹介します。
- なんでやねん(nandeya nen)
「なんでやねん(nandeya nen)」は、「なぜ」や「間違っている」という意味です。この言葉は、「ツッコミ(tsukkomi)」として、「ボケ(boke)」のおかしなところを指摘する時に使います。
- もうええわ(mō ē wa)
「もうええわ(mō ē wa)」は、「くだらない話はもう聞きたくない」という意味です。この言葉は、「漫才(manzai)」を笑いとともに締めくくる時に「ツッコミ(tsukkomi)」する人が使います。
「漫才(manzai)」で使われる主な言葉は、日本の西側の方言である「関西弁(kansai-ben)」です。これは、「漫才(manzai)」が日本の西側に位置する大阪から発展したためです。
4. 漫才はどこで見られる?
「漫才(manzai)」は「寄席(yose)」という劇場で見られます。「寄席(yose)」は全国各地にあり、有名なものは大阪や東京にあります。このほかにも、全国で放送されるお笑い番組で「漫才(manzai)」が見られます。日本では、長期休暇中や年末に「漫才(manzai)」の特別番組が放送されます。年に一度、日本一の「漫才(manzai)」の芸人を決める大会があり、その様子は全国で放送されます。この大会で優勝した芸人には賞金や賞品が贈られ、一流の「漫才(manzai)」の芸人として全国に知れ渡ることになります。若手の「漫才(manzai)」の芸人たちは、この大会での優勝を夢見て頑張っています。
5. 「漫才(manzai)」の歴史
現代の「漫才(manzai)」は、新年のお祝いの言葉を話す日本の伝統芸能に由来しています。この芸能は、約1000年以上前に始まりました。これは、笑わせることが主体ではありませんでした。現代の「ボケ(boke)」と「ツッコミ(tsukkomi)」と同じように2人1組で役割分担をして行う点は同じでした。
伝統芸能としての「漫才(manzai)」は、もともと皇居で行われていました。やがて、庶民にも広がり、大衆演芸へと変化していきました。人を笑わせるための「漫才(manzai)」は、1922年頃に始まったと言われています。
1980年頃には「漫才(manzai)」が大流行し、数々の有名な「漫才(manzai)」の芸人が活躍しました。
現代では2人1組で行う「漫才(manzai)」だけでなく、3人組で行う、「ボケ(boke)」と「ツッコミ(tsukkomi)」が途中で入れ替わる、芝居を取り入れるなど、さまざまな「漫才(manzai)」が増えています。
「漫才(manzai)」は、日本のお笑い文化のひとつとして幅広い年齢層に愛されています。日本語を学んで、ぜひ日本の「漫才(manzai)」の面白さを知ってくださいね。
実用的な日本語を経験豊富な先生のオンライン授業が無料で体験できるヒューマンアカデミー日本語学習Plusなら無料の会員登録で日本語の勉強がすぐに始められます!
カテゴリー
注目のタグ
おすすめ記事
KARUTAで
遊ぼう!
あなたはこのKARUTAの意味を知っていますか?
あなたにおすすめの記事
 若伝統文化
若伝統文化若者能を知ってますか?
2021年3月 2日
 柄伝統文化
柄伝統文化和柄とは?歴史から見えるデザインの特徴や代表的な和柄の種類を紹介
2020年12月 4日
 着伝統文化
着伝統文化着物にはどんな種類がある?格やTPOに合った選び方について解説!
2020年12月 4日
 舞伝統文化
舞伝統文化日本舞踊とは? 5大流派の特徴や起源、能や歌舞伎との関係も解説
2020年12月 4日
 舞伝統文化
舞伝統文化【歌舞伎座 鑑賞入門】歌舞伎を見るうえで事前に知っておくべきポイント
2020年12月 4日
「日本」を探検しよう
日本のことが気になる?
一緒に日本語を学びませんか?
ヒューマンアカデミーで
日本語を学ぼう!
国内最大級の学校
きめ細かなレッスンが人気!


ヒューマンアカデミーで
さらに上を目指そう!
国内最大級の学校
N1合格者多数輩出!