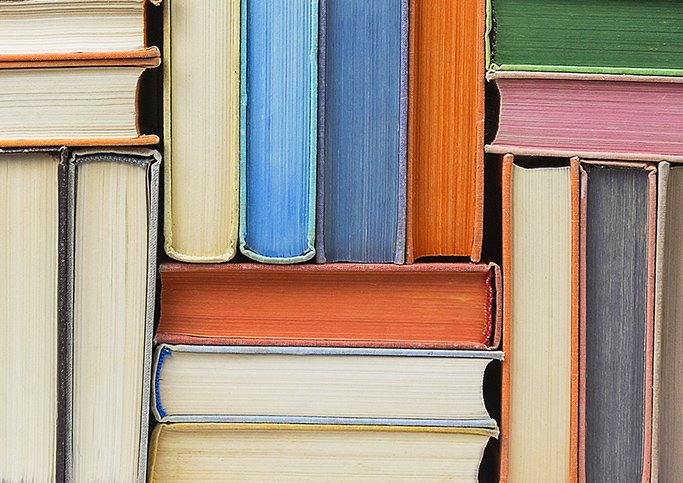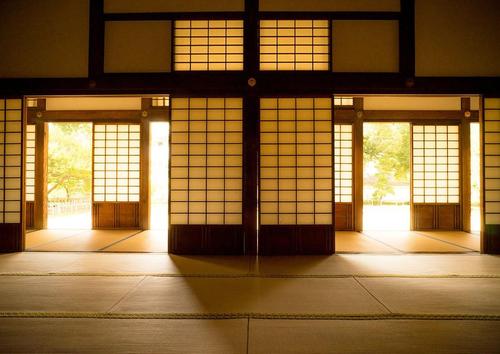wear
日本の伝統文化でもあり、伝統工芸品でもある着物。現代ではなかなか着る機会が少なく、「着物」はすべて同じように感じている方も多いのではないでしょうか?
実は、着物には様々な種類があり、TPOに合わせて使い分ける必要があります。それを知らずに場違いな着こなしをしてしまうと、恥ずかしい思いをしてしまうことに…。
今回は、着用シーンに合わせた着物の選び方を詳しくご紹介します。
着物の「格」とは?
華やかで美しい着物の魅力は、日本のみならず、海外からも高い評価を得ています。
実は着物にも、ドレスでいうフォーマル/カジュアルのような「格」があり、TPOに合わせて様々な選び方をします。
「格」には大きく分けて4種類あり、格の高いほうから順に
- 礼装着(れいそうぎ)(第一礼装)
- 略礼装(りゃくれいそう)(準礼装着)
- 外出着(がいしゅつぎ)
- 街着(まちぎ)、普段着(ふだんぎ)、浴衣(ゆかた)
と分けられています。
また、男性の着物の「格」は
- 礼装着(れいそうぎ)
- おしゃれ着(おしゃれぎ)
の2段階のみとなっています。
着物の「格」を知ることは、いわば着用シーンに合わせたマナーのようなもの。
「ハレ(はれ)」と「ケ(け)」のような特別な場面で着用する格の高い着物から、浴衣のように親しみある普段着として気軽に使える着物など、細かく分けられているのです。
それぞれの「格」を代表する着物の種類を紹介

着物は「格」ごとにさらに複数の種類があります。
それぞれの特徴や、相応しい着用シーンなどをご紹介します。
礼装着(れいそうぎ)(第一礼装)
最も格の高い第一礼装は、冠婚葬祭や公的な式典など、最も改まった席で着るものです。
◎女性の礼装着(第一礼装)
・打掛(うちかけ)
白無垢、色打掛など、挙式や披露宴に着用する花嫁衣裳。
・黒留袖(くろとめそで)
既婚女性の第一礼装。背中と両袖後ろ、両胸の5か所に家紋と、裾部分に模様が入っているのが特徴で、結婚式で親族や仲人が着用します。
・本振袖(ほんふりそで)
華麗な絵羽模様と長い袖が特徴的な着物で、未婚女性の第一礼装。総模様で、袖の長いものほど格が高くなります。成人式や結婚式、フォーマルなパーティーなどで着用します。
・喪服(もふく)
黒紋付(くろもんつき)ともいいます。五つ紋付の黒無地の着物で、お葬式にて用いられます。
◎男性の礼装着(れいそうぎ)(第一礼装)
・黒羽二重五つ紋付(くろばふたえいつつもんつき)
男性の第一礼装は、年齢に関係なく、黒地の五つ紋付に羽織・袴となります。最も格式が高く、フォーマルな場で用いられ、結婚式では花婿や仲人が着用します。
・色紋付(いろもんつき)
黒以外の着物と羽織・袴で、女性の色留袖と同格の略礼装。素材や色、紋の付け方で幅広いシーンで活躍する着物です。
略礼装着(りゃくれいそうぎ)(準礼装着)
第一礼装の次に格式の高い着物で、結婚式の披露宴、入学式などのフォーマルな場で着用します。
・訪問着(ほうもんぎ)
模様が縫い目で切れることなく、一枚の絵のように染色して仕上げた絵羽模様の着物。
・振袖(ふりそで)
未婚女性の第一礼装で、袖が長く、訪問着と同様に絵羽模様が特徴的な着物。成人式、結婚式やパーティーなどで着ることができます。
・色留袖(いろとめそで)
地色が黒以外の、裾に模様が入った着物で、既婚未婚問わず着ることができます。五つ紋付の場合は黒留袖と同格の第一礼装になり、三つ紋、一つ紋など紋の数を減らすことで訪問着や付け下げと同様に様々なシーンで用いることができます。
・付け下げ(つけさげ)
縫い目に模様が渡らないデザインで、訪問着よりも絵羽付けが簡略化された着物。訪問着より軽い外出着とみなされています。
・色無地(いろむじ)
黒以外の一色で染められた、柄のない無地の着物。一般的に一つ紋を付けることが多く、帯の選び方によっては準礼装として結婚式や茶会などで着ることができます。
・江戸小紋の紋付(えどこもんのもんつき)
遠目では無地に見えるほどの細かい柄で全体を染めた着物で、柄の大きさや種類によって格が異なります。
[記事を読んだあなたなら、このKARUTAの意味を知っているかも?]
外出着(がいしゅつぎ)
多少格があるものから趣味で楽しめるものまで、様々なシーンで着ることができる着物です。礼服ほど気負わず、しかし普段より少しかしこまった雰囲気で、おしゃれに楽しめます。
また、男性のおしゃれ着は羽織袴のありなしで幅広く調整が利くので、応用範囲が広くて便利です。
◎女性の外出着
・小紋(こもん)
全体に同じ柄が繰り返し描かれている着物。お稽古事や友人との食事など、カジュアルな外出着として用いられます。
・絞り(しぼり)
生地を糸で括ったり、器具で挟んだりしながら染色した着物。パーティーや会食というよりは、観劇や友人との食事など、気軽なおしゃれ着として用いられることが多いです。
・お召(おめし)
先染めの御召糸(おめしいと)を使って織ったもので、織りの着物の中でも最高級品とされる着物。さらっとした肌触りと、細かいシボある表面で、独特の風合いが感じられます。略礼装として着用することもできます。
・更紗(さらさ)
ペイズリー柄にも似た、南方系のエキゾチックな模様が特徴的な着物。
・無地の紬(つむぎ)
紬はどちらかというとカジュアルな着物ですが、無地の紬は絣や縞模様のある紬と比べると、多少改まった印象です。シックなおしゃれ着として、カジュアルなパーティーなどで着用します。
・付け下げ小紋(つけさげこもん)
小紋柄を染め上げた付け下げ。小紋と同格でカジュアルな部類ですが、華やかなデザインも多く、おしゃれ着として様々なシーンで活躍できます。
・小紋(こもん)(友禅)(ゆうぜん)
友禅染めで模様を描いた小紋の着物。各地域で染めや柄に様々な違いがあります。
・紬(つむぎ)の訪問着(ほうもんぎ)
素朴な地風が特徴の、軽めの訪問着。礼装ではなく小紋と同格になるので、改まったシーンよりは、カジュアルなパーティーや会食に向いています。
◎男性の外出着(おしゃれ着)
・紬(アンサンブル)
礼装着ではないので、普段着として着る場合は袴を着けずに着流しで着ることができます。外出着する際は羽織を、また改まった席では袴を着用します。結城紬、大島紬などが有名です。
・お召一つ紋付(おめしひとつもんつき)
お召や紬の無地に三つ紋や一つ紋を付けると格が上がり、女性の色無地紋付や訪問着と同格になります。略礼装として、結婚式や改まった訪問の時にも着用することができます。
・ウール(アンサンブル)
街着やプライベートな普段着として、気軽に着用できる着物。
・上布(じょうふ)
夏の着物として有名で、細い糸で織った薄手の麻織物。さらっとした肌触りで、通気性や吸水性に優れています。
街着(まちぎ)・普段着(ふだんぎ)・浴衣(ゆかた)
ちょっと外出する時などに着る、カジュアルな着物です。普段の洋服のような日常使いができます。
・絣(かすり)
所々をかすったように見える文様の着物。昔は普段着として用いられていましたが、現在ではちょっとした外出着としても親しまれています。
・銘仙(めいせん)
先染め平織りの絹織物の着物で、産地によって柄や質感に特徴があります。レトロな雰囲気のデザインが多いです。
・ウール
リーズナブルで丈夫という、日常使いにぴったりな着物。保温性があり、秋冬に活躍します。外出着ではなく家着として用いられることがほとんどです。
・黄八丈(きはちじょう)
八丈島の植物を使って草木染めされた、黄色の縞模様の着物。様々なトーンの黄色があり、美しい縞や格子柄を生み出します。
・紬(つむぎ)
節のある紬糸を使って織られた、先染めの織物の着物。絹糸なので高級品ではありますが、着物の格は低いので、友人との食事会や観劇、お稽古などのカジュアルな場面で用いられます。
・木綿
ウールと同様に普段着としては定番の着物です。気軽に洗濯ができ、お手入れが簡単なので日常着、家着に最適です。
・浴衣(ゆかた)
夏に着る、薄手の生地の着物です。着物の中でも最もカジュアルかつポピュラーなものといえるでしょう。現在は夏の花火大会やお祭りのほか、旅館などの寝巻きとして利用されています。
[日本のことが気になる?一緒に日本語を学びませんか?]
帯にも「格」がある
着物の「格」と同様に、帯にも「格」があります。コーディネートの際は、両方の格を揃えて着用しましょう。
・丸帯(まるおび)
最も格が高い帯で、第一礼装の花嫁衣裳・黒留袖・黒本振袖と合わせて着用します。
・袋帯(ふくろおび)
袋状に織られたもので、フォーマルな場面で着用します。長さは4.2m以上あり、「二重太鼓」という結び方で結びます。
・名古屋帯(なごやおび)
長さが3.6m前後の帯で、「一重太鼓」で結びます。金銀の糸や箔が入ったセミフォーマルなものからカジュアルなのものまであり、幅広いシーンで活用できます。
・角帯(かくおび)
男性用の帯で幅約20cmの帯地が二つ折りのなっている帯です。一般的に、厚みやハリのある「博多献上」が多く選ばれていて、礼装からカジュアルまでオールマイティに使えます。
・兵児帯(へこおび)
部屋着やカジュアルなシーンに使用する男性用の帯です。約74cmの大幅や約50cmの中幅のものをしごいて着用します。
このシーンにはこの着物!TPOに合った着物の選び方

着物は「好きな時に好きなものを着てよい」わけではなく、洋服と同様にTPOに合わせて着用しなくてはなりません。
格が高いパーティーにラフな着物で参加したり、反対に、カジュアルな席でかしこまり過ぎた格好をしたりしてしまわないよう、代表的な着用シーンに合わせた「着物の選び方と注意点」を合わせてご紹介します。
結婚式やお呼ばれなどのフォーマルなシーンに合わせる着物
黒留袖は、結婚式で親族や仲人が着る着物です。親族以外の結婚式に呼ばれた際には、訪問着や振袖、色留袖がおすすめです。
訪問着は全体が一枚の絵のように染められた絵羽模様で、とても華やかなデザインなので、結婚式などの改まった席にぴったりです。パーティードレスのような扱いで、格式の高い場やお呼ばれにも着ることができます。
注意点として、振袖や色留袖は、カジュアルな場面では華美になり過ぎてしまうのであまり合いません。フォーマル~セミフォーマルな華やかなパーティーで着用しましょう。
男性の場合は、黒羽二重五つ紋付や色紋付がおすすめです。黒羽二重五つ紋付は第一礼装、色紋付は女性の色留袖と同格で、改まった場で着ることができます。
七五三や入学式に合わせる着物
このようなシーンでは、略礼装の訪問着や付け下げ、色無地、お召がよいでしょう。第一礼装より格は下がりますが、紋や帯の組み合わせによっておしゃれ着から華やかな場まで幅広く対応できます。
七五三や入学式ではお子さんが主役なので、派手過ぎず地味過ぎず、淡い色合いで上品な華やぎのあるものを選びましょう。
男性では、お召一つ紋付がおすすめです。女性の付け下げや色無地のように、パーティーや改まった席の略礼装として使用することができます。
普段着としてカジュアルに着る着物
お出かけの際におしゃれ着として着ることができるものは数多く、江戸小紋や小紋、お召、紬や浴衣などがあります。気軽な食事会やお稽古などにおすすめです。
また、浴衣はリラックス着なので、夏祭りなどの気取らないシーンで着用しましょう。
男性の普段着・街着としてはおすすめなのは紬やウールの着物です。ウールの着物はリーズナブルでお手入れも簡単なので、着物初心者でも気軽に着ることができますよ。
まとめ
着物の格について、種類や着用シーンがかなり細かく決まっていることをご紹介しました。TPOと格の関係性を理解すれば、どのような場面でもスマートな着こなしができます。
紋の数や帯の格によっても全体のバランスが調整できるということもあり、「着物」の世界は知れば知るほど奥深い魅力があります。この多様な奥深さがあるからこそ、またさらに探求心をくすぐられるのではないでしょうか。日本が誇るこの着物文化を、日本に興味を持つ外国の方にも広めていけたら素敵です。
ミニレッスンコーナー
日本と日本語について学ぼう!
「90秒で分かる浴衣の動物柄の意味知ってる?」
この記事は、「にほんご日和」に掲載された記事をKARUTAにて一部再編集しています。
当サイトの内容、テキスト、画像、イラストなど無断転載・無断使用を固く禁じます。
カテゴリー
注目のタグ
おすすめ記事
KARUTAで
遊ぼう!
あなたはこのKARUTAの意味を知っていますか?
あなたにおすすめの記事
 若伝統文化
若伝統文化若者能を知ってますか?
2021年3月 2日
 柄伝統文化
柄伝統文化和柄とは?歴史から見えるデザインの特徴や代表的な和柄の種類を紹介
2020年12月 4日
 舞伝統文化
舞伝統文化日本舞踊とは? 5大流派の特徴や起源、能や歌舞伎との関係も解説
2020年12月 4日
 舞伝統文化
舞伝統文化【歌舞伎座 鑑賞入門】歌舞伎を見るうえで事前に知っておくべきポイント
2020年12月 4日
「日本」を探検しよう
日本のことが気になる?
一緒に日本語を学びませんか?
ヒューマンアカデミーで
日本語を学ぼう!
国内最大級の学校
きめ細かなレッスンが人気!


ヒューマンアカデミーで
さらに上を目指そう!
国内最大級の学校
N1合格者多数輩出!